誰よりも有名なベルルスコーニは、誰よりもイタリアを愛しているかのような振る舞いを見せつつも、結局やってきたことといえば、目先の利益ばかりを考えて自分の欲望に溺れ、国民をメディアを使って堕落させ、意のままに動かしてしまおうとする人間(=LUI)にほかなりません。そして、そんな国に住まい、暮らし、そうした人間たちに翻弄されながらも、なんとか懸命に生きていく、本当にイタリアを支える名もなき人びと(=LORO)。
ベルルスコーニの内面を描く
以前の「【11/15公開】『LORO 欲望のイタリア』ソレンティーノ監督が描く狂乱のベルルスコーニ」にて紹介した映画『LORO 欲望のイタリア』。2018年、イタリアで公開されたこの映画は、ダヴィデ・ディ・ドナテッロ賞やナストロ・アルジェント賞など、イタリアでも最も重要な映画賞にノミネートされ、複数の賞を受賞しました。
これまでも独特な世界観と圧倒的な映像美でイタリアを代表する映画監督にまで上り詰めたパオロ・ソレンティーノの監督作品であること、そして誰もが知るシルヴィオ・ベルルスコーニを題材として扱ったことなどから、イタリア国内でも多くの話題を呼び、日本でも11月15日公開されました。
この記事では、映画のレビューをしていこうと思います。書いていたら、いつの間にかかなり長くなってしまったので、前編と後編(この記事)に分けさせていただきました。
『LORO 欲望のイタリア』の感想
LORO-とはいったい誰・何なのか
LORO=彼ら・彼らの

©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
この映画のタイトルにもなっているLORO。「彼ら・彼女ら・それら」というような、3人称複数の主語になる言葉で、英語で言えばTheyと同義です。一方で、それ以外にも、「彼ら・彼女ら・それらの」という意味でも使うことができ、その場合はTheirとなります。
重要なエンディング
LOROという言葉の意味を解釈する上で、その答えになるシーンがありました。それはエンディング。大地震によって瓦礫の町と化してしまったラクイア。瓦礫の下から、埋もれたキリスト教像がゆっくりと運び出され、地面に安置されます。

教会の瓦礫の下から、吊り上げられるキリスト像

ゆっくりと置かれるキリスト像
このキリスト教像については、これよりもかなり前、ベルルスコーニが被災直後の町を訪れるシーンでも、少しだけ登場しています。この町を訪れ、「この町に、地震で家を無くした人びとのためのニュータウンを私は建設する!」と、取材に来ていたメディアに声高らかに叫ぶベルルスコーニ。その時、遠くから「教会のキリスト教像を探して!」という誰かの声が聞こえるのですが、ベルルスコーニにはその声は聞こえていないのでしょう。そのままゆっくりと町を後にしていきます。
そして町には彼の言った通りのニュータウンが完成。一人暮らしをするにはあまりにも広すぎるほどの部屋が、住民にプレゼントされたようです……

キリスト像をじっと眺める住民たち

祈るような目でキリスト像を見つめています
シーンを再びエンディングに戻しましょう。安置されたキリスト教像。そのそばで、じっと虚ろな目で遠くを見ている、または目をつぶって祈るラクイア市民たち。彼ら・彼女ら、1人1人の虚ろな表情が、長回しのカットで写されていく。

エンディング

エンディング
そしてこのカットの中で、タイトルであるLOROの文字が画面の真ん中にゆっくりと浮かび上がってくる。景色が徐々に暗転していき、エンドロール。
町には不釣り合いなほどの豪華なニュータウンができた。それでも人びとの表情は変わらず、絶望のまま。瓦礫から探し出されたキリスト像こそが彼らの気持ちそのもの。自身によって絶望に打ちひしがれた人びとが本当に欲しかったものは、こんな豪華な家で片づけることができるものだったのでしょうか。

独りよがりな欲望にとらわれるベルルスコーニ ©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
そこにできたニュータウンは、間違いなくベルルスコーニの独りよがり以外の何物でもない産物。「誰よりもイタリアを愛している」と語る、彼が国を支えているのではありません。結局この国を支え、守っているのは、エンドロールで映し出された「彼ら」=住民たち、に他ならない、ということを物語っているのではないでしょうか。
また、「彼らのもの」という視点から考えれば、住民たちは、権力に目の眩んだ人びとや金の亡者たちの、独りよがりな善や、好き放題に垂れ流された欲望によって、翻弄され続けるだけの存在に過ぎない、ということを表しているのかもしれません。
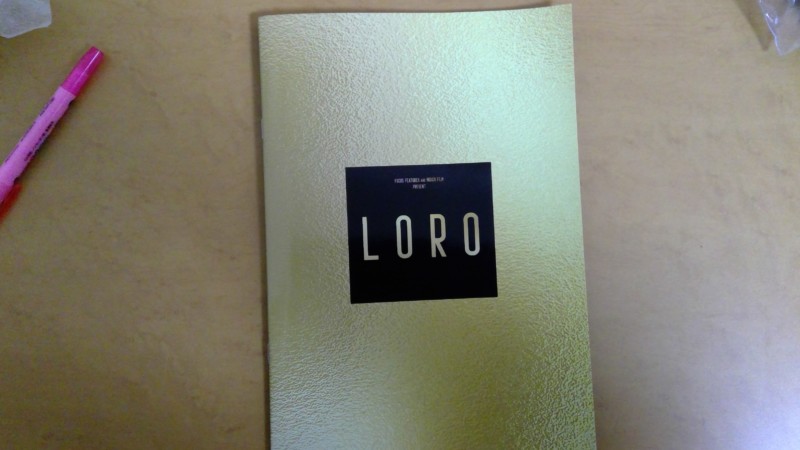
シネ・リーブル梅田で買った映画パンフレット
パンフレットを買って読んでみたのですが、「彼ら」=住民たち、という視点については、やはり触れられておりましたが、「彼らのもの」=権力者たちのモノとしての住民、という視点については特に記載はありませんでした。
映画の解釈は百人百通りの答えがあると思っているので、あくまでも個人的な意見、としてとどめておきたいと思っています。
LUIとLOROとの対比

©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
この映画のタイトル、LOROは、誰のことかがほとんど明かされずに話が進んでいきます。最後の最後までメッセージは明かされず、映画の中で意味深な描写もあまりない。「欲望のイタリア」という邦題があればこそ、推測しながら話が進められそうですが、事前知識ゼロ、LOROというタイトルだけであれば、彼らが誰を指しているかなんて分からない。ラストシーンの「LORO」というタイトルの出し方も、特別に直接的な感じはしない。人によっては「彼らって誰なんだろうね~?」なんて思いながら映画館を後にする、なんてことも全然あり得そうです。
それとは正反対に、映画の中で頻繁に「LUI=彼」と呼ばれ続ける「彼」のインパクトは絶大です。映画の前半、ベルルスコーニは全く登場しません。それどころか「Berlusconi」のBの字も出てきません。誰もが、彼を「彼」としか呼ばないのです。

ベルルスコーニの気を引くために、彼のヴィラの向かいのヴィラで開かれたパーティー ©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
「”彼”の車だわ!」
「“彼”は“彼”よ。」
「(電話の着信を見ながら)ほら、噂をすれば、“彼”からよ。」
しかし、それは明らかにベルルスコーニのことを指していることが、観ている誰もが分かるようになっています。
この見事な対比を構成したソレンティーノ監督は、すごいな、と率直に思ってしまいます。
誰か分かるけれど直接名前は出さない、名前が出ないからこそ唯一無二。小説『ハリー・ポッターシリーズ』における「名前を言ってはいけないあの人」=ヴォルデモート卿、にちょっと似ているかも。
誰よりも有名なベルルスコーニは、誰よりもイタリアを愛しているかのような振る舞いを見せつつも、結局やってきたことといえば、目先の利益ばかりを考えて自分の欲望に溺れ、国民をメディアを使って堕落させ、意のままに動かしてしまおうとする人間(=LUI)にほかなりません。そして、そんな国に住まい、暮らし、そうした人間たちに翻弄されながらも、なんとか懸命に生きていく、本当にイタリアを支える名もなき人びと(=LORO)。
映画としての評価
本国では2つの作品として公開

©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
イタリアで公開された際、この映画は『LORO 1』と『LORO 2』という2つの作品に分けて公開されました。私たちが映画館で観たのは、それを1つにまとめたバージョンのもので、少し本来の作品とは違っています。
セルジョがベルルスコーニに近づこうとする前半と、ベルルスコーニの内面に迫った後半とでは、かなり作品の雰囲気が違うのも、そういった理由があります。

©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
そのため、『LORO 1』の前半については、やはりソレンティーノ監督が何を描きたいのか、イタリアの映画評論家たちも判別しかねていた感があり、あまり評価は高くありませんでした。
一方、『LORO 2』については比較的評論家からなどの評価も高かったようです。やはり映画を観ていると、前半が少し冗長に感じられる側面もあったかな、と思うので、こういった評価についても納得です。
いずれにせよ、映画の解釈は人それぞれなので、自分にハマるイタリア映画に出会えれば、それだけで幸せだと思います。今年、映画館でイタリア映画を何本か観ましたが、僕は『LORO』が一番ハマりました(笑)
その他、雑感

©2018 INDIGO FILM PATHÉ FILMS FRANCE 2 CINÉMA
この映画を観た人が、それほど何か学びを得る、というタイプではないかもしれません。また、映画評論サイトなどでも「イタリアについての事前知識がないので、分からない部分が多かった」というコメントを見ることが多かったです。157分というかなりの長さ、ストーリーや内容も、あるような・ないような、一言で形容するのが難しい構成、そうした意味から考えても、なかなか評価をするのが難しい映画といえるのではないでしょうか。
しかし、ソレンティーノ監督自らが、「これまでも一貫して扱ってきたテーマ」と語る、「中年の人々の間の恐怖である、老いと死」という題材は、ベルルスコーニの尽きることのない、空虚な欲への渇望と、否定することのできない老いへの歩み、というそれぞれが対比される形で、より一層際立っています。
自分はまだ20代前半なので、まだまだ理解できないことばかりでしょう。この映画を30年後に観たら、違う視点を持つことができるかもしれません。
それでも、いま自分がいる場所から、彼ら=名もなき人びと、とはいったい誰なのか、何なのか、について考えてみるのは、とても面白いと思います。
さいごに
少し長くなりすぎてしまいましたが、レビューを書かせていただきました。他のイタリア映画についても興味がありましたら、この辺りの記事も読んでみてください。
関連記事
続きを見る 続きを見る
痛快!ドラッグコメディ映画『いつだってやめられる 10人の怒れる教授たち』のあらすじと魅力!

【映画 ネタバレ・感想 】『おとなの事情』誰もが触れてはいけない秘密を抱えている
